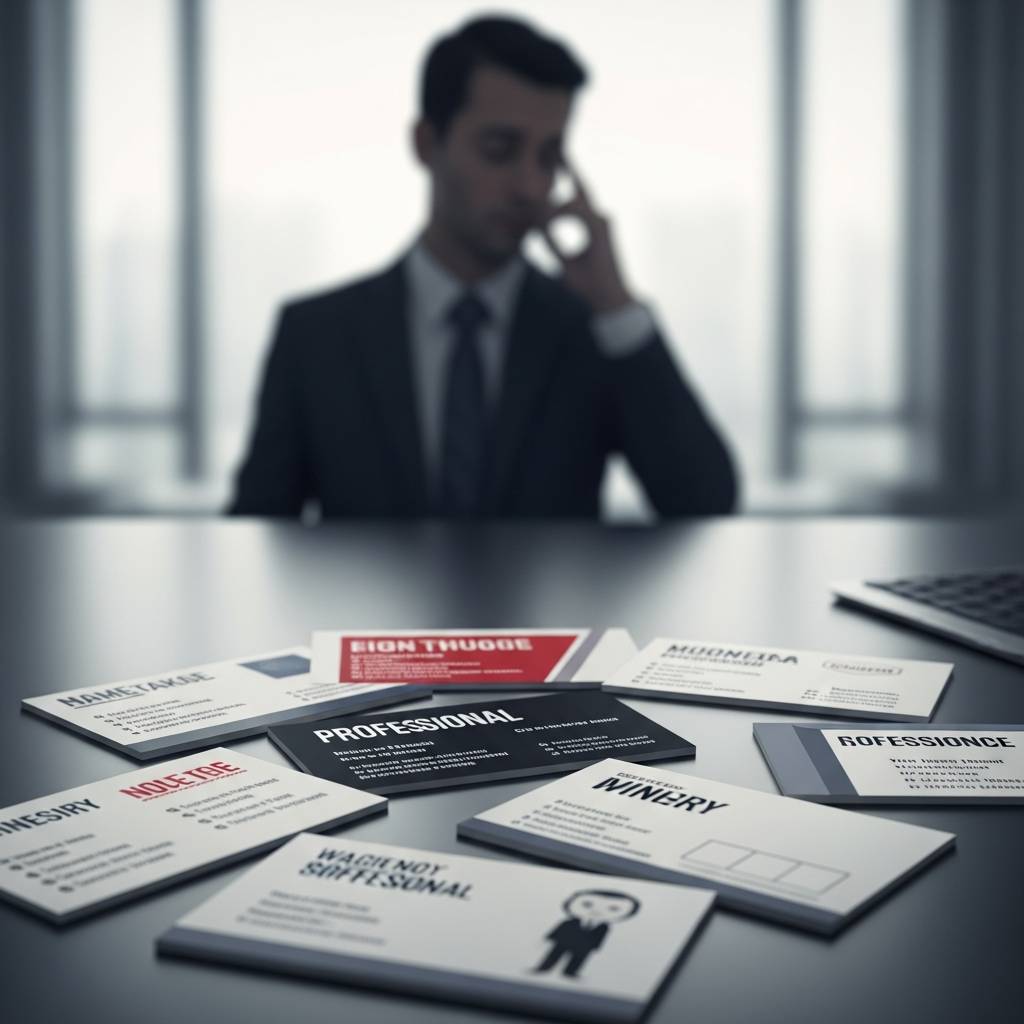名刺は、ビジネスシーンにおいて第一印象を左右する非常に重要なツールです。その中でも「フォントサイズ(何ptがベストか)」は、読みやすさ・デザイン性・信頼感に直結します。本記事では、名刺に最適なフォントサイズの目安を、用途別・要素別に専門的に解説します。
名刺のフォントサイズは何ptが基本?
一般的に、名刺で使われるフォントサイズの基本は8pt〜12ptです。ただし、すべてを同じサイズにするのではなく、情報の重要度によって使い分けることが重要です。
要素別|名刺フォントサイズの最適な目安
名刺には複数の情報が限られたスペースに配置されます。以下は、プロのデザイナーや印刷現場でもよく使われる実践的な目安です。
- 氏名:10pt〜12pt(最も目立たせる)
- 会社名・屋号:9pt〜11pt
- 役職:8pt〜10pt
- 電話番号・メール:8pt〜9pt
- 住所:7pt〜8pt
7pt以下は避けるべき理由
デザイン性を優先して文字を小さくしすぎると、可読性が著しく低下します。特に7pt以下は、印刷時のにじみや、年齢層が高い相手にとって読みにくくなるリスクがあります。ビジネス用途では最低でも7.5pt以上を推奨します。
フォントの種類によって適正ptは変わる
同じpt数でも、フォントの種類によって見え方は大きく異なります。
- 明朝体:線が細いため、やや大きめ(+0.5〜1pt)がおすすめ
- ゴシック体:視認性が高く、標準ptでOK
- 英字フォント:小さく見えやすいため注意が必要
ビジネス名刺で失敗しないためのポイント
名刺は「おしゃれ」よりも「読める」が最優先です。特に営業職や士業、医療・IT系など信頼性が重視される職種では、可読性の高いフォントサイズ設計が必須です。
まとめると、本文情報は8.5pt前後、名前は11pt前後を基準に設計すると、ほとんどのケースで失敗しません。
まとめ|名刺フォントサイズのベストバランス
名刺のフォントサイズに「絶対的な正解」はありませんが、相手が一瞬で情報を読み取れることが最重要です。印刷前には必ず実寸で確認し、実際に手に取ったときの見え方をチェックしましょう。